自由・平等・博愛の精神が間違っているのではない。
世界から自由を奪って行く病気の人がいて、人の優しい気持ちが理解出来ないだけ。
彼らは愛を知らないからね。
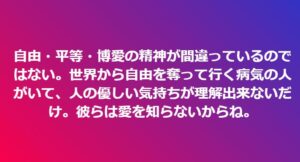
人の自由を奪う行為というのは、実は、自分もやっている恐れがある。
怒りを表現する行為は、怒りで他人から自由を奪う行為だから
気を付けないといけない。
全ては鏡だ、と言っても、それは自戒にしかならないが。
そこで、自由・平等・博愛について
再度調べることにした。以下、DMはわたし。AIはAI。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DM:自由・平等・博愛はどこから来たか?フランス革命以前の歴史を知りたい。
AI:
ご質問いただきありがとうございます。「自由・平等・博愛」の概念のフランス革命以前の歴史についてお答えします。これらの理念は、フランス革命で有名になる前から長い歴史的発展がありました。「自由・平等・博愛」(フランス語で「Liberté, Égalité, Fraternité」)の概念的起源は、主に以下の歴史的流れから来ています:
- 古代ギリシャ・ローマの思想:古代ギリシャの哲学者たちは市民の自由と平等について議論し、ストア派は人類の普遍的兄弟愛の概念を発展させました。
- キリスト教の影響:初期キリスト教は人間の平等と兄弟愛(博愛)の理念を説きました。「隣人を自分のように愛せよ」という教えはこの概念に影響しています。
- 中世の思想:カトリック神学者トマス・アクィナスは自然法に基づく権利の概念を発展させました。
- ルネサンス期:人文主義者たちは個人の価値と尊厳を強調し、自由の概念を発展させました。
- 啓蒙思想:17-18世紀の思想家たちが特に重要でした。
- ジョン・ロックは自然権としての「生命、自由、財産」の権利を主張
- モンテスキューは権力分立と自由の関係を論じた
- ルソーは「社会契約論」で平等と自由の関係を検討
- ヴォルテールは寛容と自由の重要性を訴えた
これらの思想がフランス革命前に徐々に発展し、革命期に明確な政治的スローガンとして結晶化しました。特にルソーの思想は革命家たちに大きな影響を与えました。
実際に「自由・平等・博愛」がフランス革命の公式スローガンとして広く採用されたのは、革命初期というよりも1848年の第二共和制の時代であり、その後1870年の第三共和制で正式なフランスのモットーとなりました。
より詳しい情報が必要でしたら、お知らせください。
DM:エジプトは?イシスオシリスの世界観は?
AI:古代エジプトの思想と「自由・平等・博愛」の概念の関連については、直接的な起源とは言えないものの、いくつかの関連する概念が見られます。古代エジプトのイシス・オシリス神話と関連する世界観には、後の「博愛」や「平等」に通じる要素がありました:
- マアト(Ma’at)の概念:古代エジプトでは、宇宙の秩序、正義、真実を表す「マアト」という概念が重要でした。これは社会的公正や調和を重視する思想で、ある意味で平等や正義の原初的な形と見ることができます。
- 来世における平等:古代エジプトの死生観では、死後の世界でオシリスの裁きを受ける際、王であっても庶民であっても同じ基準で魂が量られるという考え方があり、これは一種の究極的な平等観を示しています。
- イシスとオシリスの神話:イシス女神は夫オシリスへの愛と忠誠を示し、彼の死後も彼を蘇らせようと努力しました。この物語は愛と献身の象徴として解釈でき、後の「博愛」的価値観に間接的に影響を与えた可能性があります。
しかし、重要な点として、古代エジプトの社会制度自体は厳格な階層制であり、現代的な意味での「自由・平等・博愛」とは大きく異なっていました。これらの概念が政治的・社会的理念として体系化されるのは、主に西洋の啓蒙思想の時代になってからです。
古代エジプトの思想が地中海文明を通じてギリシャ・ローマに伝わり、そこから西洋思想に間接的に影響を与えた可能性はありますが、「自由・平等・博愛」の直接的な起源というよりは、人類の普遍的な価値観の一つの表現形態と考えるのが適切でしょう。
DM:インド哲学やシュメールには?あと、縄文。
AI:「自由・平等・博愛」の概念に関して、インド哲学、シュメール文明、そして縄文時代の思想における類似点や起源を探るご質問ですね。これらの文明にも関連する考え方が見られる可能性があります。
インド哲学における関連概念
インド哲学では、特にいくつかの概念が「自由・平等・博愛」の理念に通じる要素を持っています:
- アヒンサー(非暴力):特にジャイナ教や仏教で重視される、すべての生命への尊重と非暴力の概念は、一種の博愛思想と見ることができます。
- カルナー(慈悲):仏教における慈悲の概念は、すべての生き物への思いやりを説くもので、博愛の理念に近いものです。
- ダルマ(義務・道徳):古代インドの社会的道徳概念で、社会的調和を重視する思想です。
- ウパニシャッド哲学:「アートマン(個人の魂)」と「ブラフマン(宇宙の根本原理)」の一致を説く思想は、人間の本質的平等性を示唆しています。
ただし、カースト制度による階層社会が存在したため、社会制度としての「平等」とは距離がありました。
シュメール文明
シュメール文明については:
- 初期の法典:ウル・ナンム法典やリピト・イシュタル法典などの古代の法典には、社会的正義や弱者保護に関する条項があり、一定の平等意識が見られます。
- 共同体意識:都市国家における市民の共同体意識は、一種の連帯感を示しています。
しかし、シュメール社会も階層的であり、現代的な自由・平等の概念とは大きく異なっていました。
縄文時代
縄文時代の日本については、文字記録が残っていないため直接的な思想体系を知ることは難しいですが、考古学的証拠から以下のような特徴が推測されています:
- 比較的平等な社会構造:大規模な階層分化の証拠が少なく、比較的平等な社会だった可能性があります。
- 共同体の連帯:集落内での共同作業や分配システムの存在は、一種の相互扶助精神を示唆しています。
- 自然との調和:自然と共生する生活様式は、生命への尊重という点で広い意味での「博愛」に通じる要素があるかもしれません。
これらの文明や時代における考え方は、現代的な「自由・平等・博愛」の理念と直接つながるものではありませんが、人類の普遍的な価値観の多様な表現として捉えることができます。西洋の啓蒙思想における「自由・平等・博愛」が特定の政治的・社会的文脈で発展した概念であるのに対し、これらの文明にも独自の形で人間の尊厳や社会的正義に関する考え方が存在していたと言えるでしょう。
DM:日本には神官と政官の二種があったはず。この神託をもってマツリゴトをする、という精神に、自由・平等・博愛はみてとれるか?
AI:日本の古代における「神官と政官の二種」の関係と、「神託をもってマツリゴト」を行う精神の中に、「自由・平等・博愛」の要素を見出せるかという興味深い視点ですね。古代日本の政治体制では、確かに祭祀(マツリ)と政治(コト)が「マツリゴト」として一体的に捉えられていました。この点について考察してみます:
- 平等の観点から: 神事を通じて政治を行うという考え方には、権力が特定の個人の恣意的な意思ではなく、神意に基づくという思想があります。これは権力者も神(あるいは自然の法則)の前には平等であるという見方を含み、一種の権力の相対化と見ることができます。
- 博愛の観点から: 日本の古代信仰には、共同体全体の繁栄や安寧を祈る要素が強くあります。神事を中心とした「マツリゴト」は、個人の利益よりも共同体全体の調和や幸福を重視する精神を含んでおり、これは広い意味での「博愛」の精神に通じる部分があるかもしれません。
- 自由の観点から: 厳密な意味での「個人の自由」という概念は見出しにくいですが、神意に従うことで権力者の恣意的な支配から逃れるという意味では、一種の「制度的な自由」の萌芽とも考えられます。
しかし、いくつかの留意点もあります:
- 古代日本の「マツリゴト」は、現代的な意味での政教分離とは異なり、神事と政治が一体化した体制でした。
- 実際の社会構造は階層的であり、現代的な意味での「平等」とは大きく異なっていました。
- 「自由・平等・博愛」という概念は西洋近代の政治思想から生まれた特定の文脈を持つもので、そのまま古代日本に当てはめることには慎重である必要があります。
古代日本の「マツリゴト」の精神には、共同体全体の調和と秩序を重視する価値観があり、それは広い意味では人類の普遍的な社会的価値の一表現と言えます。しかし、西洋近代の「自由・平等・博愛」とは異なる形で発展した独自の価値体系として理解するのが適切でしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フランス革命だけが、自由・平等・博愛を謳ったわけではない。
人間のバランス感覚が、このトライアングルによって立つところは
歴史を見れば割とハッキリ見て取れると考える。
私の「常識」と「非常識」の狭間においては
このトライアングルから、「自由」の部位を
誰かが人民から奪う時は、きまって宗教や社会体制などの変革を通じてだし
そういった変革という言葉で、人々から自由を奪っていくように見える。
但し、その「自由」は「バランス」なんだと思う。
比率は常に変動している。
だから、特定の「愛のない個人」によって
社会が極端にバランスを崩すとき
必ず自由が失われる結果を生む。
その「自由」のバランスを支えるのは
「ひと一人の愛」であることは、経験を持つ人間なら明白。
だから、自分がどう生きるか?が常に問題なのだ。
愛を教わらなかった人間。
彼らは、決まって世の中から「自由」を奪い取ろうとする。
自由・平等・博愛のバランスを崩して、自分の思う方に世界を動かそうとする。
それらが大問題であるのは
明々白々なれど
その「問題児」をも活かして前に進むことが肝要。
そこで、いわゆる「善悪を超える」必要がある。
正義を振りかざしても無駄。正負は存在しない。
あるのはバランスだけ。そのバランスを保てるかどうかが鍵。
勧善懲悪はあり得ないからだ。
善は悪たりえるし
悪は善たりえることを考えねばならないからだ。
自分の中にバランスを生み出すことが必要。
それには、場のエネルギー感を感じる感性があるかどうか。
人ひとりを活かせるかどうか。視点・視座の問題だけだろう。
Muran











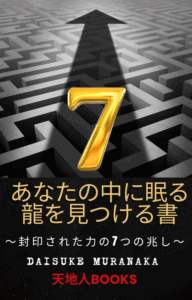
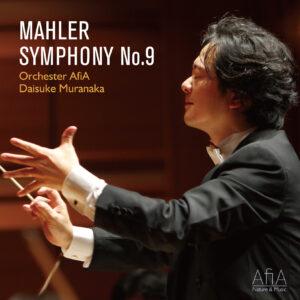
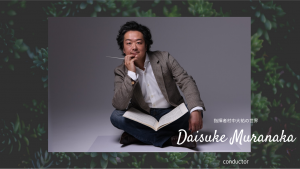
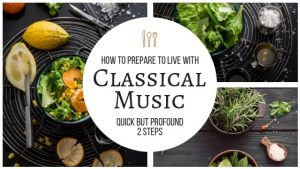

最近のコメント