ウイーンの国立歌劇場横に
Da CarusoというCD屋がある。
そこは知る人ぞ知るマニアックなCD屋だが
そこのオヤジが留学当時薦めてくれた
ブルックナー交響曲第9番のCDが
何を隠そう
シューリヒトの指揮によるウイーン・フィルとの
EMIからの録音だった。
ウイーンの人はブルックナーを自分の街の作曲家と思っており
シューベルトやマーラーとある意味同列に考える。
「ヴィーナーリッシュ」
つまりウイーン風の音楽だというのだ。
この「ウイーンらしさ」を表現できる人は
意外なことに少ないらしい。
評価の高かったのは
当時の歌劇場音楽監督アッバード。
そして往年の名指揮者
カール・シューリヒト。
いずれもシューベルトの感覚を
ブルックナーやマーラーの演奏に感じさせることのできる指揮者だ。
ブルックナーの音のなかには
ベートーヴェンの後期の弦楽四重奏やピアノソナタ、
バッハのある部分から継承した
形而上学的な要素に加え
ウイーンの自然が感じられる。
「音の中の自然」とは
すなわち
日本人にも通ずる
自然の中に神の存在を感じる感覚だ。
でもその「自然」のあり方が
微妙に違うところが
ウイーンのウイーンたる所以か。
オーストリアの自然に
日本の自然のような優しさはなく、
極めて異常に感じられる青であり緑だ。
エゴン・シーレの初期の絵にさえはっきりと表れる
鮮やかな暗さとでも言ったらいいだろうか。
そして空気の中にカビの生えた感覚。
世紀末ウイーンを象徴する
フロイトの心理学は
このカビ菌を含んだ空気から生まれたのではないか?
そう思いたくなる街の景色である。
21世紀の今でも
そこにはバロックがあり
時代の流れが止まっているように感じたのが
私の中のウイーンの記憶。
かつてフランツ・ヴェルサー・メストが
ロンドン・フィルの常任に若干30歳にして就任し
マーラーの復活の緩徐楽章の最初のリズムで
既にウイーンの響きを解き放っていたのを聴いて
本当に感激し、驚きもした。
メストはロンドンでブルックナーの素晴らしい解釈を残している。
そういう土地の色・匂いや雰囲気
いやもっというなら地霊との交信ができることは
とても重要なのかもしれない。



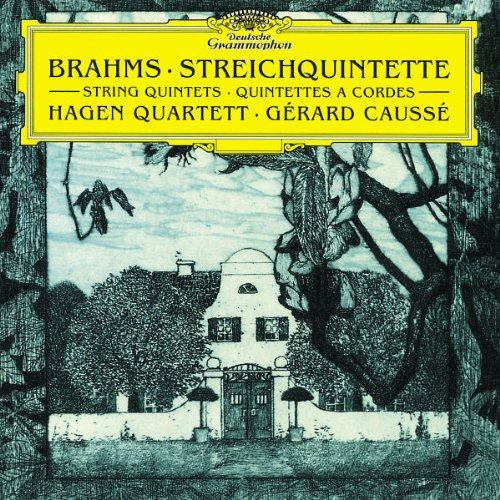


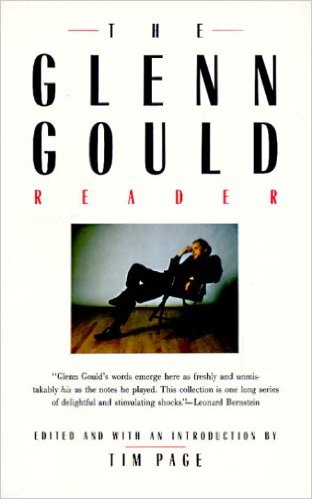

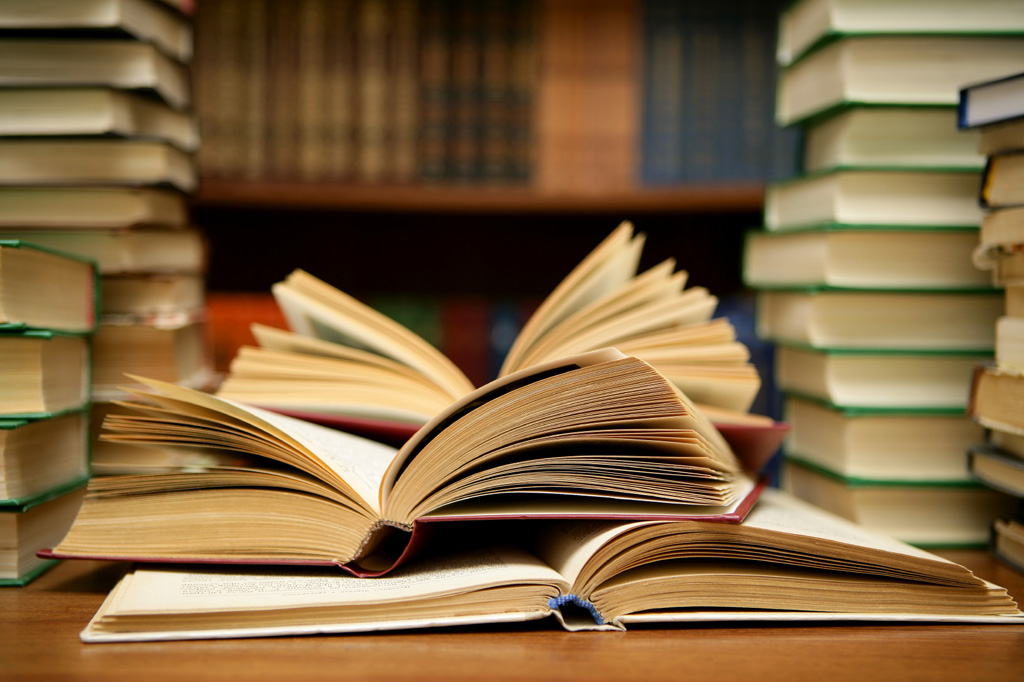







最近のコメント