ルチアーナ・セーラというソプラノ歌手とは、実は1990年代の終わりに
シチリア島のパレルモにあるテアトロマッシモで
ヨハン・シュトラウスの喜歌劇「こうもり」の仕事で一緒になった。
その時のキャストは本当に素晴らしく、パレルモの劇場が
25年間の時を経て再開されたシリーズのひとつが
この「こうもり」だったわけだ。
でも結果的にはテアトロマッシモを練習で使ったものの
公演はすべてテアトロ・ポリテアマで行われた。
私がマッシモにデビューするのはその後の「マノン」でのことだった。
いずれにせよ、マッシモ劇場再開のために
各地から最高の布陣を揃えて行われたため
アルマンド・アリオスティーニ、アンジェロ・ロメロ、レオナルド・モンレアーレ、
ルチアーナ・セーラ、ダニエラ・マッズッカートなど錚々たるイタリア・オペラ界の
重鎮ばかりが集まった。
それが私の最初のルチアーナとの出会いとなった。
考えてみれば、彼女とパヴァロッティが一緒に1983年に
ミラノにあるスカラ座でドニゼッティの「ルチア」をやった時
指揮者は師匠のペーター・マークだった。(↓にビデオがある)
でも彼女の素晴らしさはイタリアだけでなく
ニューヨークのメトロポリタン歌劇場でも存分に発揮されている。
それがこのモーツァルトの歌劇「魔笛」の夜の女王のアリア。(↓に2つビデオがある)
そしてロンドンのロイヤルオペラハウスのオッフェンバッハ「ホフマン物語」。
ルチアーナの素晴らしさは、まあ聴いてもらうとお分かりいただける。(↓にビデオがある)
マッシモ劇場の裏方の話を散々聞いたところでは、
デル・モナコやフランコ・コレッリといったテノール歌手たちは
皆が緊張していて、「俺は世界最高だ!」という自己暗示を大声で言いながら
舞台に出て行ったそうだ。これは偉大なソプラノ歌手だった
テバルディやアントニエッタ・ステラもそうだったらしい。
ところがルチアーナは違った。
何と。舞台袖でやっていたことは、「四股を踏む」ことだった。
まだ存命だから本人に訊いてみると良い。
相撲の関取のように「ドスン、ドスン」とやるわけだ。
後にも先にもこれは初めての体験。
ディーヴァだと言うのに、普通の女性に早変わりして
気さくな人柄も好感の持てるソプラノ歌手だった。
ルチアーナ・セーラの声は硬質だがフレキシブル。
クリスタルのような声の歌手は、往々にして表現力が伴わないことが多い。
ところがセーラの場合は、極めて表現力に富んだ歌唱が聴ける。
この硬質な、キンキンした声は、稀にウィーンでドラマティックなソプラノの
マーラ・ザンピエーリなどで聴くことはあった。
彼女たちはどうやって、こういう声を維持しながら成功に導いてきたのか。
非常に興味のあるところだ。日本でなら、素材自体がキンキン声なので
受け入れられないはずだ。
つまり、「遠くに響く声」という概念がヨーロッパにはあるのだろう。
近くで鳴る声「近鳴りの声」はダメとは言いながら
本当にどの声が「正解」なのかは、誰にも分からないのだ。
本人の「あるがまま」を受け入れて、それを伸ばしてやることができるか?
そこが正に勝負のような気がする。
その人間が持つ「独特の個性」をそのままに伸ばしてやる。
そういったコミュニティ側の「余裕」や「豊かさ」があって初めて
こういった声が生まれてくるのだと、痛感している。





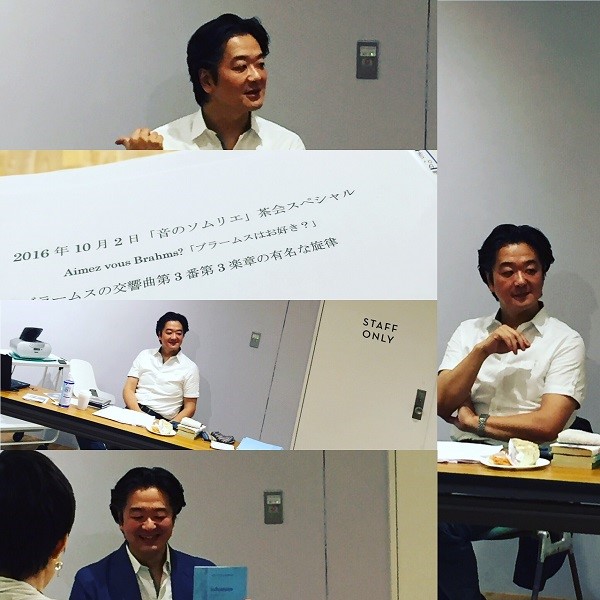


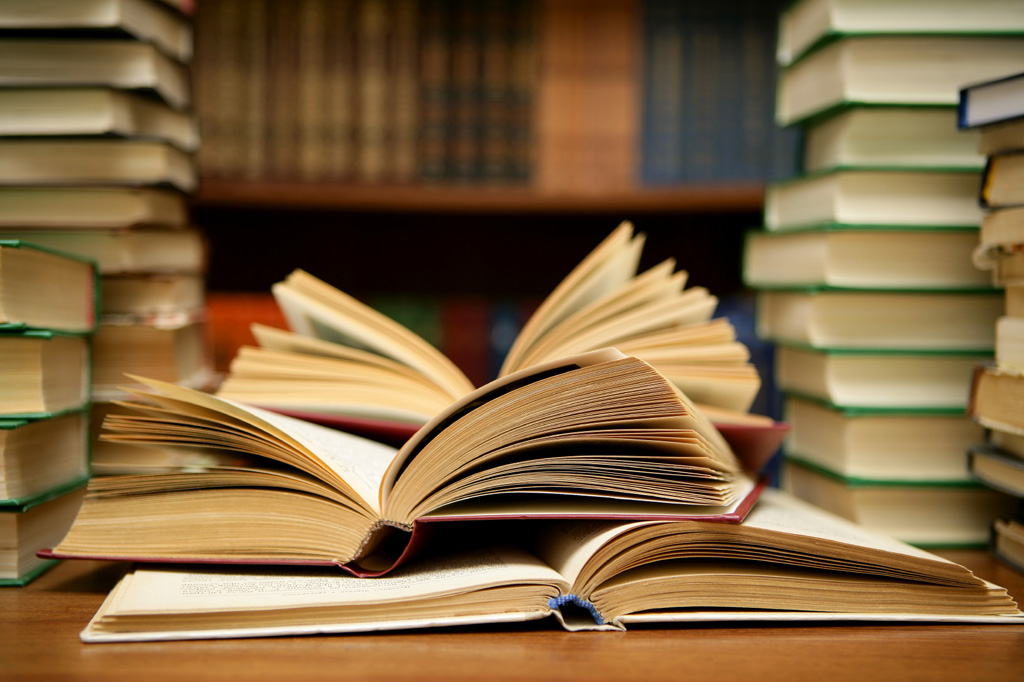

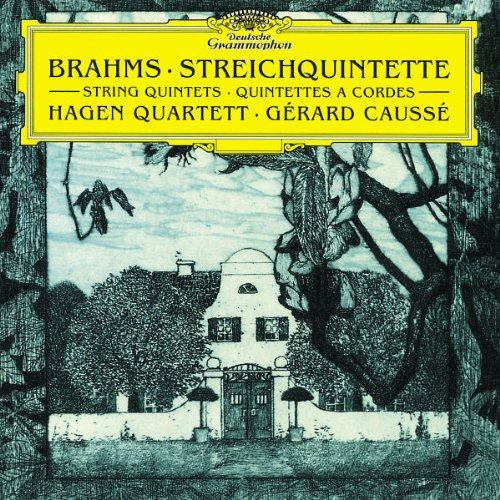





最近のコメント